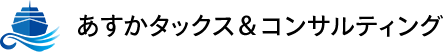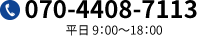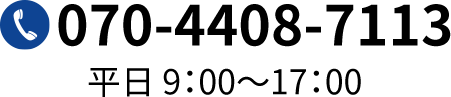「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

不動産売却時の「譲渡所得税」徹底解説!節税のコツと特例の使い方

不動産を売却するとき、避けて通れないのが税金です。なかでも大きな割合を占めるのが譲渡所得税です。
売却益に対して税金がかかることは知っていても、計算方法や節税のポイント、使える特例については意外と知られていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産オーナー向けに、譲渡所得税の仕組みや節税のコツ、特例の使い方をわかりやすく解説します。
譲渡所得税とは?不動産売却時にかかる税金の仕組み
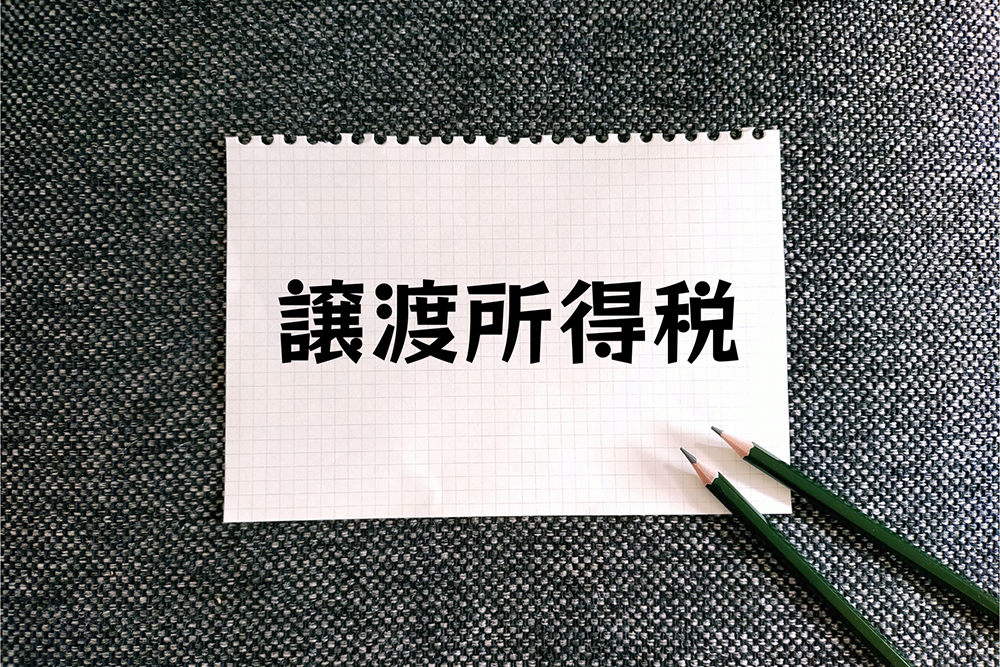
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(=譲渡所得)にかかるのが譲渡所得税です。一般的には譲渡所得税と呼ばれますが、その内訳は、所得税、住民税、復興特別所得税(令和19年12月まで)となっています。
譲渡所得税の元となるのは、譲渡所得です。譲渡所得は、以下の式で算出されます。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (物件取得費+譲渡費用)
このとき、譲渡収入金額よりも物件取得費や譲渡費用が上回っていれば、つまり、売却しても利益が出なかった場合(譲渡所得がマイナスになった場合)は、譲渡所得税はかかりません。
長期譲渡と短期譲渡の違い
譲渡所得税の大きな特徴は、保有期間によって税率が変わることです。保有期間が5年以下の場合は短期譲渡の扱いになり、39.63%(※特別復興税を含む)の税率が課せられます。それに対して、不動産の保有が5年を超えている場合は、売却すれば長期譲渡の扱いになって、20.315%(※同)の税率になります。
例えば、令和7年に不動産を売却したとします。その不動産の取得が令和元年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、令和2年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」です。
長期譲渡時と短期譲渡時の税率の差が、実際の税額にどのように反映されるか、簡単にシミュレーションしてみましょう。仮に1,000万円の譲渡所得が得られた場合、短期で売却すると税金は約390万円、長期で売却なら約200万円と、約190万円の差が出ることになります。
【長期譲渡と短期譲渡による税率の違い】
| 区分 | 保有期間 | 税率 | 1,000 万円利益時の税額 |
|---|---|---|---|
| 短期譲渡 | 5 年以下 |
所得税 30% |
約 390 万円 |
| 長期譲渡 | 5 年超 |
所得税 15% |
約 200 万円 |
※特別復興税 約200万円
※特別復興税は、基準所得税額(所得税額から、所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の金額)に2.1%をかけたもの。確定申告時に申告・納付します。
節税の鍵は「取得費」と「譲渡費用」

譲渡所得を小さくできれば、その分税金も下がります。重要なのが、経費として認められる「取得費」と「譲渡費用」です。
取得費とは?
物件を購入したときにかかった費用のことです。取得費には、以下の費用が含まれます。
- 物件の費用
- 仲介手数料
- 登記費用
- 登録免許税
- 設計費や建築費用(新築の場合)
- リフォーム費用(リフォームの場合)
なお、古い物件で領収書や契約書が残っていない場合、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなす方法もあります。ただし、実際の取得費が売却価格の5%を超える場合は、損をする可能性があるため注意が必要です。
譲渡費用とは?
売却時にかかる費用で、代表的なものは以下です。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 測量費や解体費(更地にする場合)
取得費や譲渡費用の記録を正確に残しておき、計上することで、税負担を軽くすることができます。
譲渡所得税を減らせる主な特例と要件
不動産売却には、税負担を軽くできるさまざまな特例が用意されています。代表的なものを紹介します。

1. 3,000万円特別控除
長期譲渡・短期譲渡を問わず、自宅を売却した場合、最大3,000万円までの譲渡所得を控除できる制度です。投資用不動産には使えませんが、住んでいた家を売却する場合には大きな効果があります。
気をつけなくてはならないのが、住まなくなった日から3年を経過した日が含まれる年12月31日までに売却する必要があることです(例えば、令和4年1月1日に住まなくなったとしたら、令和7年の12月31日までに売却)。
この特例は2.の特例と併用できる場合があります。
2. 特定の居住用財産の軽減税率
自宅を売却する際に、売却する年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合に適用できる特例です。1.の3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得に対して、通常の税率よりも低い、以下の税率が適用されます。
- 課税される譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分:所得税 10% + 住民税 4% = 14%
- 課税される譲渡所得のうち、6,000万円を超える部分:所得税 15% + 住民税 5% = 20%
3. 買い替え特例
自宅を売却して、新たに別の自宅を購入(買い替え)する場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べられる(先送りできる)制度です。売却した年ではなく、買い替えた不動産を将来売却した年に、まとめて課税されます。資金繰りに余裕を持たせたい場合に有効です。
4. 空き家に関する特例
相続によって取得した戸建の空き家を、一定の要件を満たして売却した場合、最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる特例です。少子高齢化に伴う空き家問題の対策として設けられました。「昭和56年5月31日以前に建築された家屋」であることなど、厳しい要件が定められています。相続した家屋が賃貸に出されていた場合は適用できません。
これらの特例は、適用条件や申告方法が複雑なため、注意が必要です。ここでは例として、上記の1の特例と2の特例を併用したパターンを見ておきましょう。
〈例〉
Aさんは、自宅(所有期間10年超)を売却して、譲渡所得が7,000万円発生しました。
この場合、適用できる特例は以下の2つです。
- 1. 3,000万円特別控除
- 2. 特定の居住用財産の軽減税率の特例
ステップ1:3,000万円特別控除の適用
まず、譲渡所得から3,000万円を控除します。
- 譲渡所得:7,000万円
- 特別控除:- 3,000万円
- 課税される譲渡所得(課税譲渡所得):4,000万円
ステップ2:軽減税率の適用
次に、この「課税譲渡所得4,000万円」に対して、軽減税率を適用して税額を計算します。
先ほど提示した税率は、以下の通りでした。
- 6,000万円以下の部分:税率14%(所得税10% + 住民税4%)
- 6,000万円を超える部分:税率20%(所得税15% + 住民税5%)
この例では、課税譲渡所得は「4,000万円」なので、6,000万円以下の部分に該当します。 したがって、適用される税率は14%です。
ステップ3:税額の計算
税額を計算します。
- 課税譲渡所得:4,000万円
- 税率:14%
- 税額:4,000万円 × 14% = 560万円
この560万円が、Aさんが納めるべき譲渡所得税(所得税+住民税)の総額となります。
売却前にできる節税対策とタイミングの考え方
不動産の売却では、売る「タイミング」が手元に残る金額を大きく左右します。特に税金面で損をしないためにも、以下の点を意識して計画的に進めましょう。

保有期間を意識する
不動産を売却した際の税率(譲渡所得税)は、物件の保有期間によって大きく変わります。税率は5年を境に変わるため、売却時期をずらすだけで数百万円単位の節税につながることもあります。
リフォームや解体費用の扱い
売却のために実施したリフォームや建物解体費は譲渡費用に含められる場合があります。無駄なく計上できるよう、領収書を保管しておきましょう。
複数物件の売却タイミング
複数の不動産を保有している場合、同じ年に売却すると、それぞれの売却益(譲渡所得)が合算されてしまい、税金が高くなることがあります。例えば、1年目は物件Aを、2年目は物件Bを売却するなど、数年に分けて売却することで、税負担を平準化できるケースがあります。ただし、物件の売却には市場の動向も関わるため、税務上のメリットだけでなく、総合的な判断が求められます。
これらの節税対策を自分だけで判断するのは難しいものです。売却を検討される際は、税金の専門家である税理士に相談し、最適なタイミングや方法をアドバイスしてもらうのが賢明な選択と言えます。
まとめ
本記事では不動産売却時にかかる譲渡所得税について、あすかタックス&コンサルティングが解説しました。不動産売却時にかかる譲渡所得税は、「保有期間や売却タイミングを工夫すること」「取得費・譲渡費用を正しく計上すること」「条件に合う特例を活用すること」の3点を押さえておくと、大きく節税することが可能です。
ただし、実際の計算や特例の適用には複雑な条件があり、自己判断で進めると「使える特例を見落とした」「税務署に否認された」といったリスクもあります。
不動産売却を検討している方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。あすかタックス&コンサルティングでは、不動産オーナー様の状況に合わせた最適な節税プランをご提案しています。「思ったより税金がかかった…」「使える特例があったことを後になって知った…」と後悔する前に、まずはお気軽にご相談ください。
代表 石井 輝光
最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)
- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日
- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日
- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日
ご相談ください
-

-

-