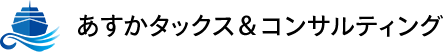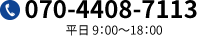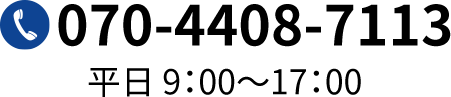「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

家賃を見直すタイミングはいつ?大家が損をしないための判断

家賃は、賃貸経営にとってもっとも重要な課題といっても過言ではありません。相場より高すぎれば空室が増え、安すぎれば収益を逃してしまいます。特に最近では、エリアの需要や築年数、周辺のリノベーション物件の増加などにより、家賃の見直しが必要となるタイミングが急に訪れることもあります。
「今の家賃は適正なんだろうか?」「このまま据え置きで大丈夫なんだろうか?」と疑問を感じたら、家賃の見直しを検討してみましょう。本記事では、家賃を見直すべきサインや、家賃を下げる際に押さえるべき経営の数字、さらに交渉対応のポイントや家賃を上げる最適なタイミングまで、初心者の大家さんにもわかりやすく解説します。
家賃の見直しが必要になる3つのサイン

家賃をむやみに変更するのではなく、見直しすべきタイミングかどうかを見極めることが大切です。以下のようなサインが見られる場合、家賃の再検討を行う必要があります。
1. 空室期間が長期化している
周辺の類似物件に比べて、新規入居者の募集期間が長い場合、家賃が相場より高い可能性があります。
例えば、周辺物件が1か月程度で成約されているのに対し、自分の物件だけが3か月経っても入居者が決まらないような場合は注意が必要です。空室が続けばキャッシュフローが悪化し、経営安定性にも影響します。
新規入居者がなかなか決まらないと感じたら、同じエリアの同条件物件より家賃が高いかどうかを確認しましょう。
2. 入居希望者から家賃相談を持ちかけられることが増えた
内見後に入居希望者から、家賃を下げてもらえないかという相談が増えてきた場合も、家賃が市場感覚とズレ始めているサインです。これはエリアの競争力が変化している可能性があるため、放置すると成約率が低下する恐れがあります。
3. 築年数や設備競争による魅力低下が進んでいる
築浅物件やリノベーション済み物件が増えてくると、同じ家賃では選ばれにくくなります。古いままだったり、設備が見劣りしたりする状態で家賃を維持するのはリスクが高く、空室や回転率の悪化が起きやすくなります。
周辺で新築やリノベ物件が増えていませんか?また、設備面で洗面台が古かったりWi-Fiがなかったりなどの弱みが目立つことはないでしょうか?
ただし、上記のサインを見つけたからといって、感覚だけで家賃を下げるのは危険です。次章では、家賃を見直す前に、まず確認すべき経営の数字について解説します。
家賃を下げる前に確認すべき経営の数字
家賃を下げると、入居者が決まりやすくなる一方で、家賃収入が下がるというデメリットもあります。そこで大切なのは、どこまで下げても経営が成り立つかを数字で把握しておくことです。以下の3つは、家賃見直しの判断をする前に必ず確認しておきましょう。
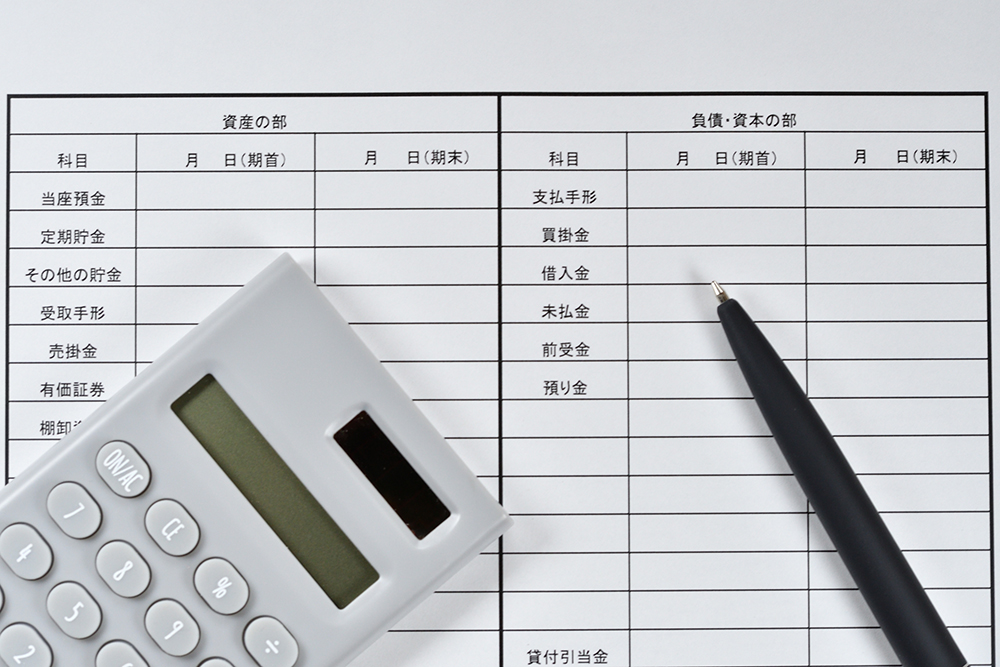
キャッシュフロー
毎月の家賃収入から、ローン返済・管理費・修繕積立・固定資産税などを引いた、実際に手元に残る金額(キャッシュフロー)を確認します。例えば、家賃1万円を下げたことで、毎月のキャッシュフローが赤字に転落するようであれば、家賃の引下げは慎重に検討すべきです。
例
| 項目 | 現状 | 1万円下げた場合 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 70,000円 | 60,000円 |
| ローン返済・諸経費 | 55,000円 | 55,000円 |
| キャッシュフロー | +15,000円 | +5,000円 |
→このように赤字にはならないが大幅に減少する場合は、下げ幅の再検討が必要です。
空室期間との損益比較
家賃を下げずに空室が3カ月続く場合と、1万円下げてすぐ入居が決まる場合では、どちらの損失が大きいのでしょうか?この判断には、空室期間による損失と家賃引き下げ後の収入減を比較することで明らかになります。
例
| 比較項目 | 金額 |
|---|---|
| 家賃7万円 → 6万円に変更した場合 | 年間▲12万円の収入減 |
| 空室が3か月続くと | ▲21万円の損失(7万円×3か月) |
⇒ この場合、家賃を下げずに空室を続ける方が損失は大きいと判断できます。
利回り(家賃見直し後の投資効率)
家賃を下げることで、利回り(投下資金に対する収益率)も下がります。そのため、家賃見直し後の利回りを試算し、許容範囲内かどうかを確認しておくことが重要です。
利回り(%)=年間家賃収入 ÷ 物件購入価格 × 100
| 項目 | 家賃7万円の場合 | 家賃6万円の場合 |
|---|---|---|
| 年間収入 | 84万円 | 72万円 |
| 利回り(例:1,200万円の物件) | 7.0% | 6.0% |
年間収入や利回りを数字で判断することなく、「空室が怖いから」「内見者から値下げ相談されたから」といった理由で家賃を下げてしまうと、キャッシュフローの悪化や経営の不安定化につながる危険性があります。家賃見直しは数字に基づいて判断することが安定経営への第一歩です。
家賃交渉への対応方法と注意点

募集時や更新時に、入居希望者や既存の入居者から、「少し家賃を下げてもらえないか?」と交渉されるケースは珍しくありません。交渉に応じるかどうかは、利益とのバランスと今後の経営安定性を軸に判断することが重要です。以下では、交渉対応の具体的な方法と注意点を説明します。
交渉に応じるべきかどうかの判断基準
値下げ交渉に応じた方がよいのは、次のような場合です。
空室が長期化している場合
上記の損益比較で見たように、空室は大きな損失になります。キャッシュフローを改善するためには、多少の減額でも早期成約が有利です。
周辺相場より高い場合
周辺や賃貸サイトの調査を行い、相場よりも物件が高い場合は、市場とのズレを解消することで入居希望者が増えることが予想されます。
長期入居が期待できる
家賃を下げることによって、入居者が長期にわたって住み続けてくれることが確認できれば、入居者の再募集リスクを抑えることができるため、交渉に応じることも考えましょう。
交渉に応じる場合の対応方法
交渉に応じ、家賃を値下げした場合でも、以下のような提案を行うことで、長期的には利益を安定させることができます。
長期入居を条件とする
値下げを打診された際に、家賃値下げと引き換えに、入居期間を一定期間(例:2年)以上とすることを賃貸借契約の特約事項として提案しましょう。定期借家契約でない限り、入居者は契約期間中でも解約権を持ちますが、特約事項として盛り込むことで、長期入居の意思を確認できます。家賃の値下げはオーナーにとって痛手でも、次の空室期間を心配する必要がなくなり、経営が安定します。
新規入居者に対してはフリーレントを1か月付ける
フリーレントとは、入居後、一定期間の家賃を無料にするというものです。家賃が7万円の場合、仮に1か月、フリーレントにしても、8か月以上住んでもらえれば、家賃を1万円値下げするより、総収益は上回ります。入居後の一定期間、10%から30%程度、家賃を割引するキャンペーン割引も有効な方法です。
値下げをしない代わりに入居者に有利な設備を追加する
Wi-Fiや宅配ボックス、食洗機の導入など、入居者が価値を感じられるような設備を導入する方法もあります。賃貸オーナーにとって、設備を導入するための費用はかかりますが、入居満足度がアップすることで長期入居が期待できます。
このように単純に家賃だけを下げるのではなく、総収支を考えながら競争力を高める選択肢を検討することが大切です。
家賃交渉の注意点

家賃交渉に応じて、入居者も納得できる条件を提示する際には、その進め方や記録を適切に行わないと、後々大きなトラブルや不利益につながる可能性があります。合意した内容は、入居者双方が署名・押印して保管しましょう。特に賃貸オーナーは、以下の3つの点に注意して対応を進めてください。
交渉の結果は必ず書面に残す
口頭での合意は、言った、言わないの水掛け論になりやすく、将来的なトラブルの原因にもなりかねません。家賃の値下げや、上記のような長期入居の特約やフリーレントや割引などの条件を合意した場合は、必ず以下の形で証拠を残してください。
- 新規契約・更新時: 賃貸借契約書に特約事項として明確に記載する。
- 契約期間中の家賃変更時:賃貸条件変更合意書などの書面を作成し、賃貸オーナー(または管理会社)と入居者の双方が署名・押印して保管する。
周辺相場と公平性を常に意識する
特定の入居者に対してのみ大幅な値下げを行うと、他の入居者との間に公平性の問題が生じる可能性があります。周辺相場より極端に安い家賃に設定すると、物件全体の価値(評価額)を下げることになり、将来的な売却や融資の際にも不利になる可能性があります。
また、特定の入居者のみを値下げすると、ほかの入居者から不満が出て、同じように家賃を下げてほしい、などの要求が出てくるリスクもあります。そのような場合に、長期入居を約束してもらったなど、交渉に応じた明確で合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。
安易な恒久的な値下げは絶対に避ける
一度家賃を下げてしまうと、賃貸借契約の性質上、オーナーの都合で簡単に元の家賃に戻すことはできません。これは、借地借家法により入居者の居住権が強く守られているためです。地域の経済状況が回復し、周辺相場が上昇しても、一度下げた家賃を元の水準に戻すのは非常に困難です。将来の収益機会を失わないよう、恒久的な値下げは慎重に判断しましょう。
家賃交渉への対応は、目先の利益だけでなく、物件の市場価値、地域相場、そして賃貸オーナーのキャッシュフロー全体を考慮して判断する必要があります。特に、相場と比較して、自分の物件の適正価格が判断できない場合や、提示すべき条件が法律上問題ないか判断できないようなときは、専門家に相談することが最善策につながります。
家賃を上げるベストなタイミングとは?

家賃の見直しは下げるだけでなく、上げる判断も重要です。以下のようなサインが見られる場合、適正範囲内での家賃アップを検討できる可能性があります。
周辺相場が上昇しているとき
東京都下をはじめとして、埼玉県、千葉県、京都市、福岡市など、都市部の賃貸マンションの家賃は、上昇を続けています。アットホームの2025年8月 全国主要都市の賃貸マンション・アパート募集家賃動向によると、30平米以下のシングル向けマンションでは、福岡市や東京23区では、前年同月比で10%を超え家賃が上昇しています。都市部にある賃貸物件のオーナーにとって、値上げの好機といえるでしょう。
まずは周辺の賃貸サイトなどで同条件の物件を調査することから始め、相場との乖離が5%以上あったら、値上げの検討を始めましょう。
設備投資やリフォームで価値が向上したと感じられるとき
入居者が、今までより価値が上がったと感じられるタイミングは、値上げを伝えやすくなります。なかには、比較的お金をかけずに価値のアップを体感できる改修もあるため、家賃値上げを検討する賃貸オーナーは、設備投資やリフォームを考えるのも一つの方法です。
【値上げ根拠になりやすい改善例】
| 改善内容 | 入居者の感じるメリット |
|---|---|
| 無料 Wi-Fi 導入 | 毎月の通信費節約 |
| 浴室・洗面台・キッチンのレンジフードなどの交換 | 快適性向上 |
| セキュリティ設備導入 | 安心感アップ |
| 宅配ボックス、食洗機、浴室乾燥機の導入 | 利便性向上 |
| 外壁・共用部の美観改善 | 管理意識の高さをアピール |
日ごろから入居者の声に耳を傾け、入居者が求めている改善策を取ることで、満足度も上がり、家賃アップをしたとしても、入居者も納得しやすくなります。
更新時(長期入居者への調整)
長く住んでくれている入居者は退去リスクを考えると値上げを言い出しにくいものですが、周辺相場が上がっている場合は、適正化するためにも値上げが必要です。更新のタイミングで文書を出し、家賃の値上げを伝えましょう。
ポイントは、近隣相場の上昇など、値上げの根拠をはっきりと書くこと。併せて、値上げ=負担ではなく、今後の安心と管理品質の維持のため、というトーンを強く打ち出すことが重要です。家賃を上げることは無理なお願いではありません。価値の向上や市場動向に応じた適正化として提案することで、初心者オーナーでも無理なく実現できます。
まとめ
本記事では、賃貸物件のオーナーに向けて、家賃を見直すタイミングや、大家が損をしないための判断基準について、あすかタックス&コンサルティングが解説しました。
家賃の見直しは、空室が怖いから、あるいは、ちょっと古くなってきたから、といった感覚で行うと、収益悪化や経営不安定につながります。重要なのは、家賃の見直しが必要になるサインを見逃さず、経営の数字をチェックし、交渉時は条件調整を検討すること。また、値下げばかりでなく、タイミングによっては家賃の値上げも考えましょう。
家賃調整は、大家経営において大きな分岐点です。ひとりで判断に迷う場合は、税務面を含めた経営全体の視点からのアドバイスを専門家に求めましょう。
代表 石井 輝光
最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)
- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日
- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日
- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日
ご相談ください
-

-

-