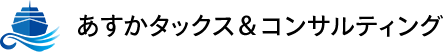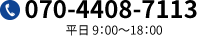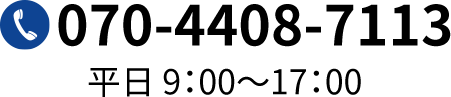「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

公務員が不動産投資するメリット・デメリット

公務員は安定した職業とされていますが、将来の生活や資産形成のために副収入を得たいと考える人も少なくありません。しかし、公務員の副業は原則的に禁止とされているため、副収入を得る手段も限られます。
そこでご紹介したいのが、不動産投資です。副業規定を守りながら計画的に不動産投資を行うことで、資産形成も可能になります。本記事では、公務員が不動産投資を行う際のメリットとデメリットを詳しく説明し、公務員に適した戦略を紹介します。
公務員が不動産投資するメリットとデメリット
公務員ができる副業は限られていますが、不動産投資は公務員でも可能な副業の手段の1つです。ここでは公務員が不動産投資するメリットとデメリットを整理しておきましょう。

公務員が不動産投資するメリット
公務員による不動産投資のメリットは、主なものとして、以下の3つがあります。
公務員は高い与信力がある
不動産投資を始める際に、多くの投資家は不動産投資ローンを利用して物件を購入します。その際に、公務員の給与は安定しており、景気の影響を受けにくいため、不動産投資の際に高い信用力(与信)があるとみなされます。この与信力の高さから、銀行からの融資を受けやすく、低金利でローンを組みやすいという大きな強みがあります。
管理業務を管理会社に委託できる
不動産投資を行い賃貸物件の「大家」になったとしても、実際の管理業務は管理会社に委託することができます。不動産の運用には、入居者の募集から始まって、物件の維持・管理、クレーム対応など多くの業務が発生しますが、管理会社に業務委託することで、管理業務に時間を割くことなく、本業に集中できます。
将来の資産形成につながる
公務員は定年まで雇用が保証されていることが多いですが、過剰な業務や異動の多さなどから、転職を考える人も少なくありません。また、定年まで勤めあげても、退職後の不安を感じる人もいます。しかし、不動産投資を活用すれば、家賃収入を得ることで、転職や退職後の生活を支える資産を築くことができます。

公務員が不動産投資するデメリット
不動産投資についてはデメリットも存在します。不動産投資をうまく進めるためにも、デメリットを知っておきましょう。
副業規定に抵触する可能性がある
公務員には原則として副業が禁止されており、投資の方法によっては規定に違反する可能性があります。適切な方法(後述)で投資を行わないと、何らかの処分を受けるリスクがあるため注意が必要です。
初期費用や維持費がかかる
与信力の高い公務員は、銀行から多額の融資を引き出すことができます。しかし、不動産会社に勧められるまま、初期費用や維持費がかかることを考えずに融資枠いっぱいの高額な物件を購入すると、期待していた収益が得られない場合もあります。
空室リスクがある
不動産投資では、借り手がいない期間が続くと家賃収入が得られず、ローンの返済や維持費の負担が重くなります。不動産投資ローンの返済を続けながら収益を出し、資産経営をするには、立地や物件選びを慎重に行うことが重要です。
不動産の所有が5棟10室以下である場合
公務員の副業に関する規定は厳しく、原則として営利目的の活動は禁止されています。ただし、不動産投資においては以下のような場合、不動産投資は可能です。
- 不動産の所有が5棟10室以下である場合
- 年間の家賃収入が500万円未満の場合
- 管理業務は委託している場合
- 相続によって不動産を取得した場合
それぞれについて詳しく見ていきましょう。

不動産の所有が5棟10室以下である場合
人事院規則14-8によると、賃貸物件を「5棟」か「10室」所有していると、アパート経営は副業ではなく「事業」とみなされます。
そのため、国家公務員が不動産投資を行う場合、戸建て物件なら4棟以内、ワンルームマンションなら9室以内であれば、「事業」ではないとみなされ、運用が可能となります。ただし、地方自治体によっては独自の取り決めが定められている場合があるため、担当部署に確認を取っておきましょう。
年間の家賃収入が500万円未満の場合
同様に人事院規則14-8では、「不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合」は「事業」とみなされることが定められています。
例えば、家賃10万円のワンルームマンションを4室運用する場合は、全室満室でも400万円であり、人事院の規則に抵触しません。5室になると500万円になってしまうため、人事院の規則に抵触してしまいます。
管理業務は委託している場合
国家公務員法や地方公務員法では、公務員が職務に専念するために、事業を運用したり、営利企業に従事したりすることを禁じています。不動産投資の場合でも同様で、上記の範囲内であれば保有することは認められても、管理業務を兼業することは認められていません。そのため、管理業務に対しては、管理会社に完全に委託することが求められます。
相続によって不動産を取得した場合
公務員の副業規定では、基本的に営利目的の活動が禁止されていますが、相続や贈与によって取得した不動産の所有は特例として認められる場合があります。相続や贈与は、自らの意思で不動産を取得したのではなく、家族や親族から引き継ぐ形で所有するため、副業としての「営利活動」とはみなされにくいからです。
しかし、規模が大きい場合(一般的に「5棟10室ルール」と呼ばれる基準)には、勤務先に相談し、管理を適切に行うことが重要です。
公務員の安定した収入を活かした不動産投資戦略
公務員が不動産投資を行う際には、リスクを抑えた戦略が重要です。

少額からスタートする
いきなり高額な物件を購入するのではなく、少額で始められる物件から投資をスタートすると、リスクを抑えることができます。
具体的な投資方法としては、以下のものがあります。
区分マンション投資
ワンルームや1Kなどの区分マンションは、比較的少額(数百万円~数千万円)で購入できるため、初心者向けといえる。
中古物件の活用
新築よりも価格が低く、利回りが高い傾向にある中古マンションやアパートを選ぶのも良い。ただし、リフォームなどの費用は見込んでおかなければならない。
REIT(不動産投資信託)
不動産を直接購入せず、少額(数万円~)で不動産市場に投資できる。
長期保有を前提とする
不動産投資において、短期間で売却益(キャピタルゲイン)を狙う「短期売買」は市場の変動リスクが大きく、失敗する可能性があります。一方で、長期保有(インカムゲイン重視)の戦略を取ることで、安定した家賃収入を得られ、リスクを抑えることができます。
長期保有のメリットとしては次のことがあります。
- 景気変動があっても、家賃収入を継続して得ることができる
- 税制優遇が受けられる
- 安定したキャッシュフローを確保できる
管理を委託する
副業規定に抵触しないよう、賃貸管理会社に運営を委託するのも有効な方法です。管理業務を第三者に任せることで、規定違反のリスクを回避しながら、物件の適切な維持・管理が可能になります。また、専門の管理会社に依頼することで、入居者対応や賃料回収、修繕対応などの負担を軽減できるため、本業に支障をきたす心配も少なくなります。
反面、管理会社に委託する場合は、当然のことながら手数料がかかります。全面的に委託する場合の管理手数料の相場は、家賃収入の約5%とされており、その分も見込んで資金計画を立てる必要があります。
まとめ
本記事では公務員の不動産投資について、あすかタックス&コンサルティングが説明しました。公務員が不動産投資を行うことには、安定した収入を活かせるという大きなメリットがある一方で、副業規定の遵守やリスク管理が不可欠です。慎重に計画を立て、適切な投資戦略を取ることで、安全に資産形成を進めることが可能になります。不動産投資を検討している公務員の方は、まずは専門家に相談しながら、ルールを守った適切な投資を目指しましょう。
代表 石井 輝光
最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)
- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日
- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日
- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日
ご相談ください
-

-

-