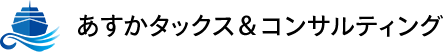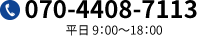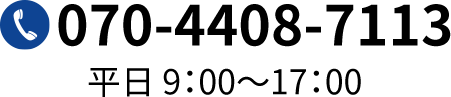「永遠の繁栄へと導く経営革新ブログ」

不動産オーナー必見!倒産防止共済は節税に使えるって本当?
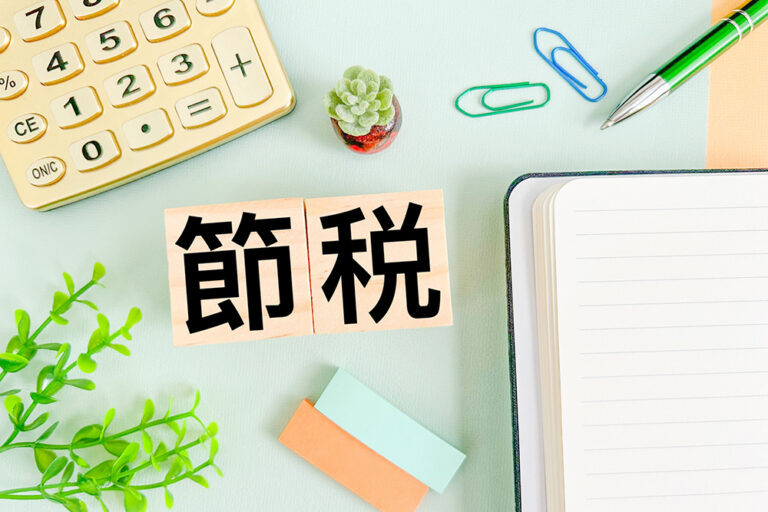
不動産オーナーにとって、「節税」は常に頭を悩ませるテーマではないでしょうか?利益が出ているのは喜ばしいことですが、その分税金も増えるため、いかにして合法的に手元に残る資金を増やすかは重要な課題です。そんな節税対策の一つとして、「倒産防止共済」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、「本当に節税になるの?」「どんな制度なの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、不動産オーナー様が知っておくべき倒産防止共済の基本から、節税効果、さらには資金繰り対策としての活用法まで、詳しく解説します。
倒産防止共済とは?制度の基本をおさらい

「倒産防止共済」とは、正式名称を「中小企業倒産防止共済制度」といい、中小企業庁が所管し、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する共済制度です。取引先企業の倒産などによって連鎖倒産等の事態に陥ることを防ぎ、中小企業の経営の安定を図ることを目的としています。
この制度の大きな特徴は、毎月掛金を積み立てていくことで、万が一取引先が倒産して売掛金や受取手形などが回収不能になった場合に、積み立てた掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で共済金の貸付けが受けられる点にあります。これにより、急な資金繰りの悪化から自社を守ることができます。
倒産防止共済は、その名の通り「倒産防止」を目的とした制度ですが、掛金が税法上の取り扱いにおいて大きなメリットをもたらすことで、多くの企業から節税対策としても注目されています。次章では、この共済がなぜ節税につながるのか、そのメカニズムと具体的なメリット・デメリットについて詳しく掘り下げていきます。
共済加入は節税につながる?メリット・デメリット
「倒産防止共済の掛金がなぜ節税になるの?」その秘密は、掛金の税務上の取り扱いにあります。
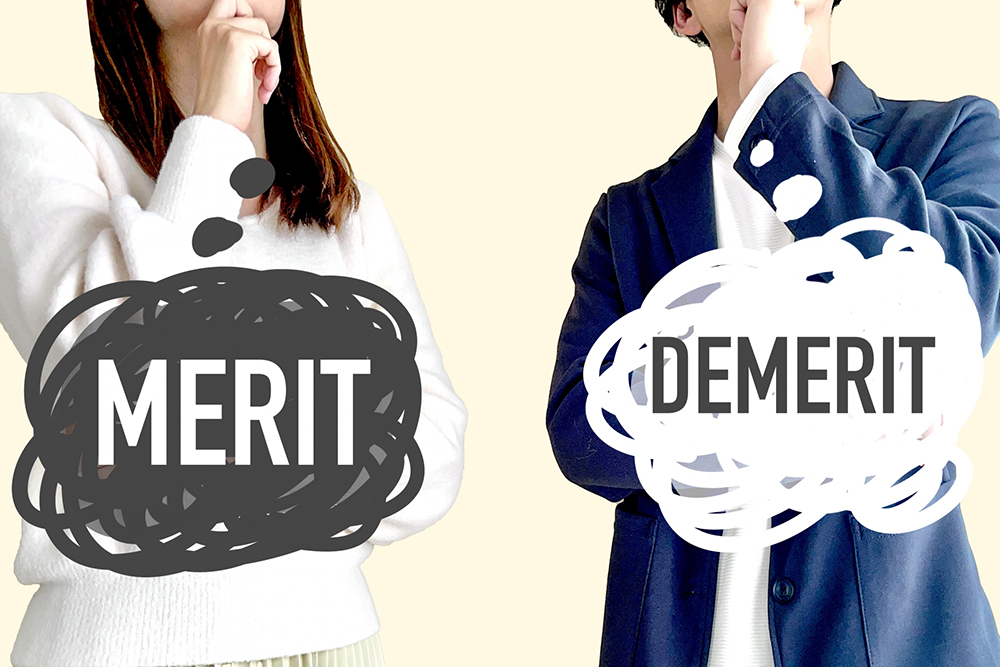
共済加入のメリット
共済加入によるメリットは、主に節税効果と緊急時の資金調達の2点があります。
全額損金算入による節税効果
倒産防止共済の最大の魅力は、支払った掛金の全額を法人税法上の損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入できるという点です。
掛金は月額5,000円から20万円の範囲内、5,000円刻みで自由に選べますが、例えば、毎月20万円、年間240万円の掛金を支払った場合、その240万円は会社の利益から差し引かれ、課税対象となる所得が減少します。その結果、支払う法人税や住民税を抑えることが可能です。
不動産管理会社設立による節税についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
不動産オーナーは不動産管理会社を設立して節税しよう
緊急時の資金調達
倒産防止共済は、緊急時の資金調達として利用できます。
取引先の倒産時に無担保・無保証人で貸付
本来の目的である倒産防止機能も忘れてはなりません。取引先が倒産し、売掛金や受取手形が回収できなくなった場合、積み立てた掛金の10倍(最高8,000万円)の範囲内で、無担保・無保証人で共済金の貸付けを受けることができます。これにより、連鎖倒産のリスクを回避し、事業の継続を支援してくれるという、まさに「備えあれば憂いなし」の制度です。
40ヶ月以上の加入で解約返戻金が100%に
倒産防止共済は、あくまで「もしもの時」のための共済ですが、万が一の事態が起こらず、共済を解約することになった場合でも、一定期間加入していれば掛金が戻ってくる仕組みになっています。具体的には、掛金納付月数が40ヶ月以上であれば、解約手当金として支払った掛金の全額が戻ってきます。
これにより、掛金は「使途が限定された預金」のような感覚で捉えることもできます。もちろん、解約時に戻ってきたお金は益金として計上されるため、その年度の課税対象となりますが、利益を繰り延べる効果や、いざという時の資金源として活用できる点が魅力です。
デメリット:中途解約時の元本割れと資金の拘束
一方で、倒産防止共済には中途解約による元本割れや、資金の流動性の低下、解約益への課税といったデメリットも存在します。
中途解約時の元本割れ
前述の通り、40ヶ月未満で共済を解約した場合、支払った掛金が全額戻ってきません。特に12ヶ月未満の場合は掛け捨てになってしまいます。
| 掛金納付期間 | 任意解約時(※)の解約手当金の支給率 |
|---|---|
| 12ヶ月未満 | 掛け捨て |
| 12ヶ月以上23ヶ月 | 掛金の80% |
| 24ヶ月以上29ヶ月 | 掛金の85% |
| 30ヶ月以上35ヶ月 | 掛金の90% |
| 36ヶ月以上39ヶ月 | 掛金の95% |
| 40ヶ月以上 | 掛金の100% |
(※契約者が任意に解約する任意解約のほかに、契約者の死亡や会社の解散などによる「みなし解約」、滞納による「機構解約」があり、支給率が異なるため、詳しくは専門家にご確認ください)
このように、1年未満での解約は、大きな損失となる可能性があります。無理のない掛金設定を心がけ、長期的な視点で加入を検討することが重要です。
資金の流動性の低下
共済の掛金は、一度拠出すると原則として解約するまで手元には戻ってきません。つまり、その資金は事業の運転資金など、他の用途には使えなくなるため、一定期間資金が拘束されることになります。急な資金需要が発生した場合に備え、手元の流動資金とのバランスを考慮しておきましょう。
解約益への課税
40ヶ月以上加入し、解約によって掛金が全額戻ってきた場合、その解約手当金は解約した事業年度の益金として計上され、課税対象となります。節税効果は「利益の繰り延べ」という側面が強いため、解約時にまとまった利益が発生し、課税される可能性があることを理解しておく必要があります。
節税だけじゃない!資金繰り対策としての使い方
倒産防止共済は、その名の通り「倒産防止」が主な目的であり、節税効果はあくまでその付随的なメリットと捉えることができます。しかし、この制度は単なる節税ツールにとどまらず、実は不動産オーナーの資金繰り対策としても非常に有効に活用できます。

1. 一時貸付金制度で急な資金需要に対応
倒産防止共済には、加入者が積み立てた掛金総額の範囲内で、「一時貸付金」として資金を借り入れられる制度があります。これは、取引先の倒産といった特定の事由がなくても利用できるのがポイントです。
たとえば、
- 不動産修繕の緊急出費: 突然の設備故障や大規模な修繕が必要になった際、手元の資金が足りない場合に活用できます。
- 突発的な空室対策費用: 予期せぬ退去による原状回復費用や、次の入居者を見つけるための広告費などに充てることも可能です。
- 不動産取得税などの支払い: 不動産購入後の税金支払いなど、一時的に大きな資金が必要になる場面でも役立ちます。
この一時貸付金は、担保や保証人が不要で、低金利で借り入れられるのが大きなメリットです。金融機関からの融資に比べて審査に時間がかからず、比較的スムーズに資金を調達できるため、いざという時の心強い味方になります。
2. 掛金の「出口戦略」としての活用
前述の通り、倒産防止共済の掛金は40ヶ月以上積み立てると全額が解約手当金として戻ってきます。これを「出口戦略」として活用することで、計画的な資金繰りが可能になります。
例えば、数年後に予定している大規模修繕や、新たな不動産投資の頭金など、将来的に大きな資金が必要になることが分かっている場合、それまでの間、倒産防止共済に掛金を積み立てておくという方法があります。
こうすることで、
- 毎年、損金算入による節税効果を享受しながら、
- 資金を使わずに内部にプールし、
- 必要な時期が来たら解約し、まとまった資金として活用する
といった戦略が立てられます。解約時には益金となりますが、その年の利益状況を見ながら解約時期を調整することで、税負担をコントロールすることも可能です。
不動産管理会社でも活用できる?適用条件と注意点

さまざまなメリットのある倒産防止共済は、不動産オーナーが運用する不動産管理会社でも加入し、活用することができます。ただし、いくつか適用条件と注意点がありますので、詳しく見ていきましょう。
適用条件:中小企業であること
倒産防止共済は、「中小企業倒産防止共済制度」という名称の通り、中小企業を対象とした制度です。具体的な適用条件は以下の通りです。
- 資本金の額または出資金の総額が3億円以下の会社
- 常時使用する従業員の数が300人以下の会社
不動産管理会社の場合、多くはこの条件を満たしていると考えられます。例えば、社長一人で設立したような管理会社であれば、資本金も従業員数も問題なくクリアできるでしょう。
また、法人格がない個人事業主の不動産オーナーも加入できます。その場合は、以下の条件に該当する必要があります。
- 常時使用する従業員の数が5人以下のサービス業
- 常時使用する従業員の数が20人以下の商業・サービス業以外
多くの不動産オーナー様は、これらの条件のいずれかに当てはまるため、個人事業主であっても倒産防止共済の利用を検討する価値は十分にあります。
注意点:不動産収入の安定性と本業との関連性

不動産管理会社で倒産防止共済を活用する際に、特に注意しておきたい点がいくつかあります。
1. 取引先の倒産リスクと共済金の必要性
倒産防止共済は、本来、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度です。不動産管理会社の場合、主な取引先は不動産オーナー(会社自身の場合も含む)や入居者、あるいは修繕業者などになります。
例えば、管理を委託している業者が破産し、管理報酬が回収不能になったり、滞納家賃の保証ができなくなったりといったケースは考えられます。しかし、業種によっては通常の事業会社と比べて、大規模な連鎖倒産のリスクが低いと感じるかもしれません。
この点を踏まえ、「本当に共済金の貸付を受ける必要があるのか」という視点も持ちつつ、あくまで節税や資金繰りのメリットをどこまで重視するかで判断することが大切です。
2. 不動産管理会社としての事業実態
不動産管理会社を設立している場合でも、単に不動産オーナー個人の所得分散や相続対策のために作られたペーパーカンパニーのような実態がない会社だと、税務上問題視されるリスクもゼロではありません。倒産防止共済の加入そのものが問題となるわけではありませんが、会社としての事業実態が伴っているかどうかが重要になります。
ただし、賃貸管理業務、修繕手配、入居者対応など、きちんと事業活動を行っている不動産管理会社であれば、問題なく倒産防止共済を活用できます。
3. 他の節税・資金繰り対策とのバランス
倒産防止共済は非常に有効な制度ですが、これだけが唯一の節税・資金繰り対策ではありません。小規模企業共済やiDeCo、各種保険、役員退職金積み立てなど、他にも様々な選択肢があります。
ご自身の不動産経営の規模や利益状況、将来のライフプランに合わせて、これらの制度をどのように組み合わせるのが最適かを考えることが重要です。税理士などの専門家と相談しながら、総合的な視点で最適なプランを立てることをお勧めします。
まとめ
ここまで、不動産オーナーの皆様に向けて、倒産防止共済が単なる倒産対策に留まらず、節税や資金繰り対策としても非常に有効なツールであることを、あすかタックス&コンサルティングが解説しました。
倒産防止共済は、万が一の事態に備えつつ、計画的に資金を積み立てながら節税メリットも享受できる、まさに一石二鳥の制度と言えるでしょう。特に利益が出ている年にまとまった金額を積み立てることで、効果的に税負担を軽減し、手元に残る資金を増やすことが可能です。
ただし、中途解約時の元本割れのリスクや、解約益への課税といったデメリットも理解しておくことが重要です。ご自身の経営状況や将来の資金計画に合わせて、この制度を最大限に活用できるか、慎重に検討することをお勧めします。
あすかタックス&コンサルティングでは、不動産オーナーの税務・会計に関するお悩みを解決し、最適な節税対策や資金計画をご提案しています。倒産防止共済の活用はもちろん、お客様の状況に合わせた具体的なアドバイスをご提供できますので、ご興味がありましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
代表 石井 輝光
最新記事 by 代表 石井 輝光 (全て見る)
- 不動産投資は本当に節税にならない?知らないと損する誤解と仕組みを解説 - 2025年12月25日
- 不動産投資は若いうちに始めるべき?20代・30代が有利な理由を徹底解説 - 2025年12月25日
- 法人化の落とし穴!不動産を個人名義から法人名義に移すときの注意 - 2025年11月27日
ご相談ください
-

-

-